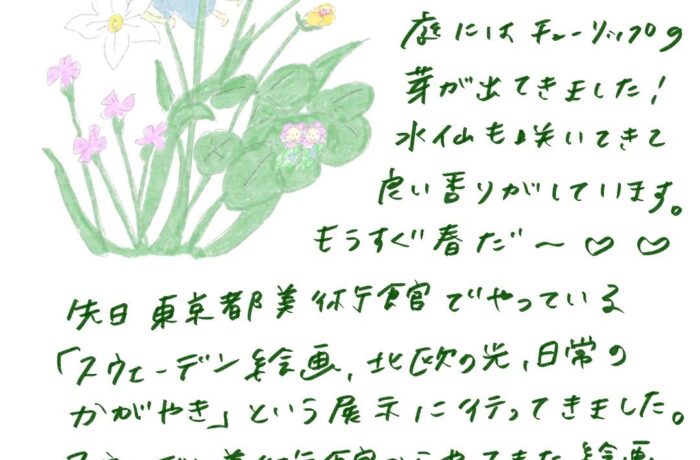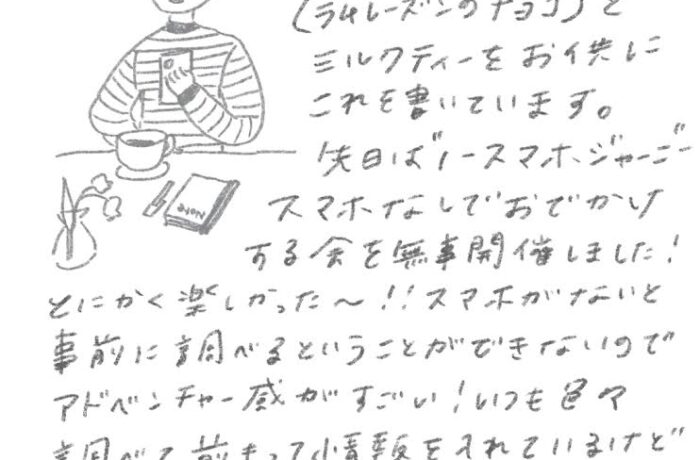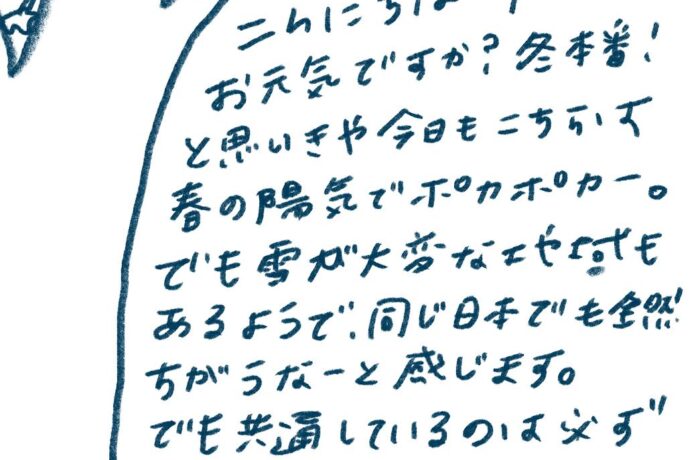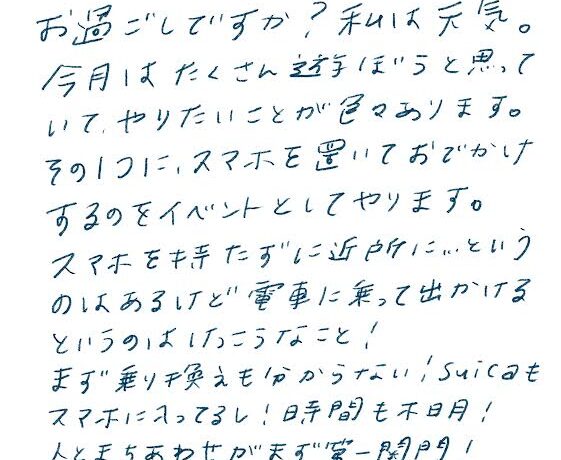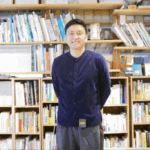

東京台東区の谷中を拠点に活動する「HAGISO」は、「最小文化複合施設」という独自の概念を提唱し、カフェやギャラリー、ホテルといったさまざまな機能を併設する空間を展開しています。実はもともとこの場所は、築68年の木造アパート「萩荘」でした。設計から店舗運営まで手がける設計事務所・株式会社HAGISOの代表・宮崎 晃吉(みやざき・みつよし)さんが、東京藝術大学の学生時代に、萩荘に住んだことがきっかけです。
まちに根差したお仕事を続ける上で大事にしていること、そして2024年11月に出版したHAGISOさんの歩みをまとめた書籍『最小文化複合施設』(真鶴出版)について、宮崎さんにお話を伺いました。
「続けること」が、まちの信頼に

──HAGISOさんは、単に建物を建てるだけではなく、住むこと、食べること、集まることなど、人が暮らして生きていく上でのさまざまな場面に寄り添うようなお仕事をされていらっしゃいます。まさに「世界に誇れる日常を生み出す。」というキャッチフレーズの通り、谷中から新しい日常が生まれていっているのではないかと思います。
宮崎さん:建築をやっていると、晴れ晴れしい特別な建築物を作ることが前面に出がちです。でも人の人生のほとんどの時間って、どこか特別な場所にいる時間よりも、普通に暮らしている時間の方が長いですよね。
日本には、非日常的な特別な日を「晴れ(ハレ)」、日常的な普通の生活を「褻(ケ)」と表す言葉があります。「褻」の、なんてことない「日常」をどう過ごすかの方が、長い目で見ると大事なんじゃないかと考えているんです。
HAGISOのキャッチフレーズは、「最小文化複合施設」です。HAGISOを立ち上げた当初、東京には巨大資本による立派な“文化複合施設”が、次々と建てられていました。我々は、もっと身の丈にあった日常に寄り添う“文化複合施設”を作ろうと、ある種の自虐を込めて、「最小文化複合施設」を名乗り始めたんです。
──宮崎さんご自身が「日常」を大事にしたいと思ったきっかけはあるんでしょうか?
宮崎さん:僕は群馬の前橋の出身です。農地と住宅地の際のような郊外のニュータウンで生まれ育って、出かけるとなると車でショッピングモールに行って、ただ買い物をして帰ってくるというのが当たり前。そうした生活につまらなさを感じていたんです。
一方、父の実家は東京の武蔵小山。僕が子どもの頃は商店街や銭湯がまだたくさん残っていて、そこで交わされるコミュニケーションがすごく新鮮だったんです。人と人とが本音で関わるようなシーンが少ないという、子ども時代に抱いていた“下町コンプレックス”のようなものが、根底にあるのかもしれません。

──HAGISOは、谷中にあった「萩荘」というアパートから誕生しました。谷中は、個人商店や多くの寺院が集まっている寺町として、そして今では年中国内外から多くの人が訪れる人気観光地の一つとして知られています。宮崎さんが大学時代に初めて谷中に住んだ当初、まちに対してどんな印象を持ちましたか?
宮崎さん:「萩荘」に住み始めた20年ほど前は、まだ谷中が今のように観光地化しておらず、東京なのにゆっくり時間が流れている感じがしました。人は高密度に住んでいるんだけどのんびりしているというのが、最初の印象です。
──そのまちでHAGISOを立ち上げることになった宮崎さんですが、まちの方たちとの関係作りで大事にされてきたことはありますか?
宮崎さん:HAGISOを始めた当初は、「地元の人がお店に来るのは3年経ってからだと思うよ」と言われたことがありました。最初は地元の方も「どうせ潰れるだろう」と様子を見ていたんだと思います。
実際に3年くらい経つと、徐々に地域の人の顔が見えるようになっていって。5年ぐらい経つと、地元に代々住んでいる若者がアルバイトに来てくれて、そこから親世代との関わりも生まれるなど、リアルな付き合いがどんどん広がっていきましたね。
「続けること」が大事なんだろうなと思います。
また僕自身、「萩荘」に住んで以来20年以上、住まいはずっと谷中です。町会に参加していますし、子どもも地元の小学校に通っています。一つの地域の中でいろんなレイヤーのコミュニティに参加しながら、日々暮らして働いています。
──3年、5年とご商売を続け、宮崎さんご自身の暮らしも谷中に根ざす中で、時間が信頼に変わっていったのでしょうね。
時間が重なり視点が交わることで、まちの奥行きが生まれる

──HAGISOさんは、谷中のまちに溶け込みながらも、個性豊かな空間をつくっていらっしゃいます。まちの雰囲気を活かす部分、自分たちらしさを残す部分などのさじ加減で、意識されていることはありますか?
宮崎さん:ステレオタイプな「谷中っぽさ」「下町っぽさ」に忖度してしまうと、まちの楽しみ方が消費的になってしまって、まち自体の面白さを発見することにつながらないと思うんです。歴史的に積み重ねられてきた都市構造は尊重しながら、そこに自分たちが今やりたいことを掛け合わせていくというのが、僕らのスタンスです。
──そういったスタンスは、地域と日常的に関わり続けている宮崎さんご自身の視点にも表れていると感じます。以前、宮崎さんのご案内で谷中のまちを歩いたことがありましたが、観光客ではない「日常」の目線で谷中を見ることができたのは、印象的でした。
宮崎さん:村田さん(筆者)と一緒に谷中を歩いたときの気づきがすごく大きくて。鉢植えや隙間から偶然生えた植物といった視点でまちを見ると、20年以上谷中に住んでいても、まだまだ新たな発見があるんだと驚きました。
村田さんだけでなく、きっとあらゆる人がまちに対してそれぞれの見方を持っていて、それが全て新鮮なんだろうなと思います。
注:筆者・村田は、街角の植物や路上にはみ出た園芸を記録し続ける“路上園芸鑑賞家”です。

──誰かが用意したイメージではなく、ひとりひとりのまちの見方にこそ、新たな魅力が潜んでいるのかもしれませんね。
宮崎さん:消費的なまちの見方だと、どうしても「このまちは●●だ」というふうに歯切れの良いコンセプトが重視されがち。もちろん、そうしなければ伝わらない面もあるのでしょうが、長い目で考えると、簡単に伝わってしまうことほどつまらないですよね。
画一的な文句を強く出すのではなく、時間が作った“重層した深み”こそ意味があるんじゃないかなと思っています。それをしっかりと見つけられる目を持ち続けたいですね。
──その点でいうと、「TAYORI(台東区谷中3丁目12−4)」では、生産者さんが書いた手紙を読めたり、お店を訪れたお客さんが生産者さんにお手紙を残すことができたりしますね。

宮崎さん:都市のように人が集まって暮らしている場所は、予期せぬ出会いも含めて面白いと思っています。消費に迎合した場所は、お金さえ払えば何でも思い通りになります。一方で、お店のルールを守らなければ追い出されてしまう一筋縄ではいかない店もある。
こうした場所も、都市の奥行きを作っているんじゃないかと思います。お金だけではないルールが存在する場所があることが面白いですし、自分のものの見方・感じ方が変わるチャンスに結びついているとも思います。
単に売る・買うを超えた予期せぬ出会いこそ、まちを訪れる価値にもつながるんじゃないでしょうか。それは、トップダウンの資本主義的な論理では作れないですよね。
すでにある豊かさを発見し続ける

──昨年11月には、これまでのHAGISOさんの歩みをまとめた書籍『最小文化複合施設』(真鶴出版)を出版されました。出版後は、どんな反響がありましたか?
宮崎さん:僕らは、外から見ると結構キラキラして、うまくやっているように見えるらしいんですが、本を読んでくれた人からは「結構泥臭くやっているんですね」と驚かれることが多かったです。本に登場するスタッフは、「あ、本の中のあの人ですね!」とお客さんに言われることもあるようです(笑)。
──そういう声を聞くと、読者へ届いている感覚がありますね。
宮崎さん:もうひとつ、実は本を作る中で、スタッフに一番読んでほしいな、という思いもありました。HAGISOは最初は5人で始めて、寝食を共にするような状態だったので、みなまで言わなくても言いたいことは伝わっていました。
その後、関わる人数が増える中で徐々に伝わらなくなるようになり、創業5年目頃のタイミングで一度、大事にしたい社訓をフィロソフィーとして言語化したんです。ちゃんと思いを外に出して、共通する指針を持つのは大事だなと常々感じてきました。書籍は言ってみれば、その延長線上でもありますね。
これまでの文脈や、いろんな人との偶然の出会いや支え、応援があってこそ、今のHAGISOがあるということを、スタッフに知っておいてほしかったんです。

──書籍は、これまでの歩みを記録するだけでなく、HAGISOというチームにとってのひとつの“旗”のような存在にもなっているのですね。そんなHAGISOのみなさんが思い描く、まちの未来の姿はありますか?
宮崎さん:HAGISOとしては、谷中に根ざした仕事と、そこで得た知見を外に生かしていくような仕事とを両軸でやっていくんだろうなと思っています。
谷中でどれだけ新しい発見をしていけるかが問われているでしょう。僕らはまちを構成する一つの要素でしかありません。何かを提供するというよりは、すでにある豊かさを見つけて顕在化させる。おそらくそのぐらいしか僕の人生の中ではできないですし、それで十分すぎると思っています。
──最後に、HAGISOでのご経験を通して、宮崎さんご自身の人生観に何か変化はありましたか?
宮崎さん:HAGISOを始める前は、海外で大規模な建築作品を作る建築家のもとで働いていたので、自分がやるべき仕事もそういうことなんだろうと思っていました。
ですが徐々に、誰かの大きな理想像ではなく、小さい工夫が積み重なったような場所にこそ惹かれていったんです。
谷中でご縁をいただき、拠点を持って10年以上活動していると、自分がコントロールできないことを含めて、本当にいろんなことが起きました。それを受け入れて生きるしかないという鍛錬にもなりましたね。
本来の建築や都市計画は、コンセプトを作って自然環境や人の流れを制御し、予定通りに使わせるかを考えることが仕事。でも現実には予期せぬことが起こるし、計画通りにはいかないことばかり。自分がいかに変化し、その時々の状況に合わせて柔軟にやっていけるかを受け入れる心持ちが養われました。
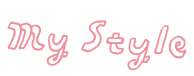

9歳と5歳の男の子ふたりの父親でもある、宮崎さん。「子どもを見ていると、人間はこのぐらい脳天気でもいいんだなと、自分がその時思い悩んでいることがどうでもいいことに思えてきますね」とのこと。お子さんの成長を見守るのが、至福のひとときだそうです。
ライター講座のお知らせ
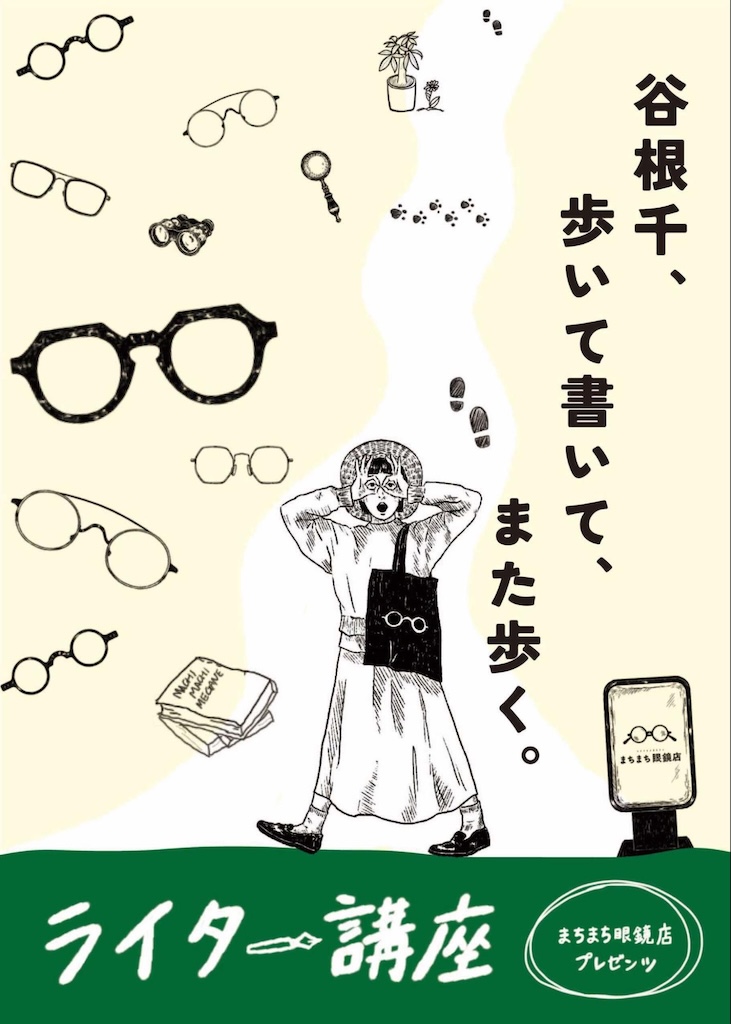

HAGISOが運営する谷根千のローカルメディア「まちまち眼鏡店」がライター講座を開催!
HAGISO代表・宮崎晃吉さんが、ゲスト講師として登場されます。また筆者である路上園芸鑑賞家・村田あやこも、ゲスト講師を務めます。
まちを編集する出版社 千十一編集室 代表でありローカルメディアの専門家・影山裕樹氏をはじめとした谷根千ゆかりのユニークな講師陣のレクチャーを受けながら、人を惹きつける文章の書き方や、まちまち眼鏡店での投稿にあたって必要なワードプレスの操作を学び、講座終了後、まちまち眼鏡店 公式ライターとしてコミュニティの一員になることができます。さらに谷根千のまちを歩き記事を書く過程を通して、普段は知ることのできない谷根千の意外な魅力に出会うことも。
また講座参加者には出版業界のプロによるトークイベント、路上観察マニアによるまちあるきツアー、NIGHT KIOSKでの共通ボトルキープなどの豪華特典が!まちまち眼鏡店ライター講座に参加して、あなたもまちまち眼鏡店編集部の一員になりませんか?
詳細・お申し込みはこちらから。