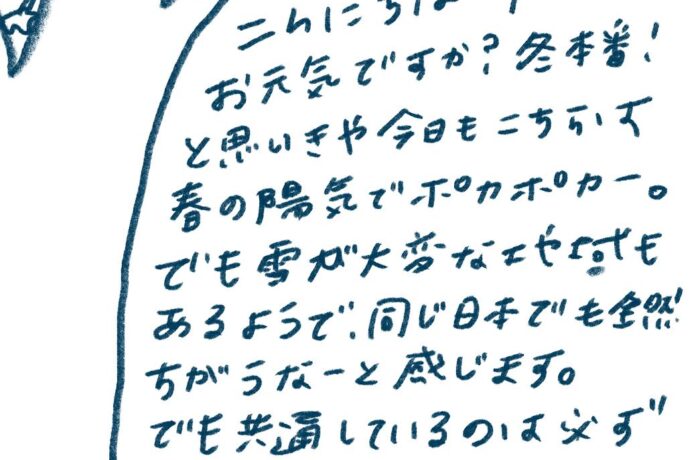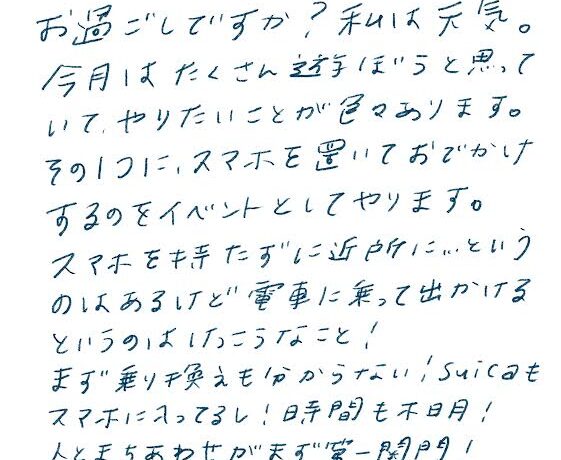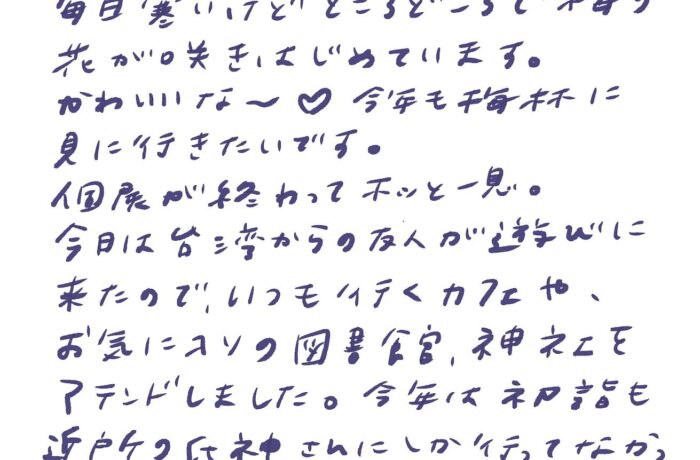「真鶴出版」は、神奈川県南西部の小さな港町・真鶴にある、”泊まれる出版社”。出版社として書籍や雑誌などの出版物を手掛けながら、宿泊施設を運営しています。
真鶴には、バブル期以降の急激なリゾート開発からまちを守るために制定された、「美の基準」と呼ばれる独自のまちづくり条例があります。今でもこの条例は息づき、昔ながらの生活風景がまちの表情をしっかりとつくり出しています。
真鶴出版にとっての「美」とは。真鶴で育んできた、暮らしと仕事の関係性とは。
2015年に真鶴に移住し、パートナーの來住 友美さんとともに真鶴出版を立ち上げた川口 瞬さんに、お話を伺いました。
入口を狭くして、情報を濃い状態で届ける

──真鶴出版さんは「泊まれる出版社」というキャッチコピーの通り、出版業と宿泊業を営んでいらっしゃいます。出版と宿泊を組み合わせようと思ったきっかけは?
川口さん:もともと真鶴に移住するタイミングで、僕が出版業、妻が宿泊業を別でやる予定だったんです。物件を探しながら屋号をブレストしていく中で、ふと「真鶴出版」として出版と宿泊を一緒にやったらおもしろいんじゃないかと思って。すぐに「泊まれる出版社」というコピーも思いつきました。
──宿泊することで本を読む時間も生まれ、出版と宿泊は親和性が高そうです。実際にはじめてみて、いかがでしたか?
川口さん:当初は何も考えず、とりあえずやってみたのが正直なところだったんですが、良かったなと思うことが色々あります。例えば出版業は、宿泊業の情報発信の役目を果たしています。出版業を通して真鶴出版を知ってくださった方が、直接ホームページから予約してくださる、というサイクルができました。
あとはリアルな話だと、複数の入金サイクルを組み合わせられる点もメリットです。宿泊業の場合は日々入金されますが、受け入れられる人数に限りがあるので、月の上限金額も決まっています。一方で出版業の場合、入金のタイミングは遅いんですが、やればやるほど稼げる、天井がないビジネスとも言えます。
宿泊業をやっていることで、あれこれ手を出すことなく、自分たちの理念に沿った仕事だけをやっていけるんです。
3年ほど前から書店業にも力を入れていて、大きな柱になりつつあります。ショップスペースでは、知り合いやうちに泊まりに来てくれた方など、できるだけつながりのある方や、自分たちがいいと思うものを増やしていっています。

──真鶴出版さんを知った上でここにいらっしゃる方は、大事にしている思いや価値観が共通する方が自然と集まってくるようにも思えますね。いい相乗効果がありそうです。
川口さん:一般的には、メディアに取り上げてもらって、たくさんの人に知ってもらおうとするのがメジャーですが、僕らは間口を広げるのではなく「入口を狭くする」ということを意識しています。それが、自分たちと価値観の合う人たちを呼び込むことにもつながると思っています。
例えば出版物は基本的に、独立系書店といって、店主が自ら選書している書店を中心に、直接卸しています。入口を狭くしているからこそ、僕らを知っている店主が、店主の知っているお客さんに本を売って……と、情報が濃い状態で届くんです。
昔ながらの生活風景は美しい

──真鶴には「美の基準」という独自の景観条例があります。単に住むだけではなく人が集まる場を作っていく上で、どのように「美の基準」を取り入れていかれたんでしょうか?
川口さん:「美の基準」は、69のキーワードで、真鶴らしい景観に馴染むにはどうすればいいかが書かれている条例です。今いる2号店も、美の基準に倣って、いかに昔からそこにあったような状態にできるかを意識して作りました。
例えば窓は、近所の郵便局から、建て替え工事の際にいただいたものです。外観には、建物から出た廃材も再利用しています。また通りに面した大きな窓があるので、前を歩く人が気にならないよう、入口を低くして目線が合わないようにしています。
他にも小松石を洗面石に使ったり、ヒラメ漁で使わなくなった錨を地元の作家さんに頼んで扉の取手にしていただいたりと、真鶴のものを建物の部材として使っています。

──様々な面で、地域に馴染む工夫が施されているんですね。「美の基準」では、生活を形作る風景が「美」と捉えられてるのが印象的です。川口さんご自身が思う「美」とは、どのようなものでしょうか?
川口さん:道端に干物や海苔を干していたり、ひじきを煮ていたり。道祖神の前を通り過ぎるときにすっと手を合わせたり。そういう昔ながらの生活風景はいいなあと思いますね。そこから季節も感じられて。

──真鶴のまちを歩いていると、個人宅でありながら、玄関前のアプローチや建物一角の井戸を、ご近所の方が使えるよう開放しているおうちがあったのが印象的でした。「背戸道」と呼ばれる路地を登った景色のいいところには、休憩できるベンチが置いてあったり。場所やものを自分だけで独占せずに共有し合って、いい意味での境界の緩やかさがあるのが、真鶴らしい暮らしの風景を作っているのかな、とも感じました。
川口さん:真鶴の皆さん、コミュニケーション能力が高いと感じています。相手が困っていないか様子を察し合って、絶妙な距離感でスッと手を差し伸べてくれて。今も日々学んでいますね。
最近では、文字化されていないまちでの振る舞いやしきたりについて、分からないことがあると、ご近所の情報感度の高いおばあちゃんに「この場合ってどう対応したらいいですか?」と聞いています。
──指針を示してくれる方がいるのは安心できますね。何かを共有し合うというのも、そうした機微や暗黙知で細やかに運営されているんでしょうね。真鶴出版さんで手掛ける出版物の佇まいにも、川口さんが思う「美」を取り入れているんでしょうか?
川口さん:「美の基準」の美しさとは、いわゆる真っ白なギャラリーに絵を1枚だけ飾ったのとは、ちょっと違う美しさだと思っていて。例えば石の階段に生えた苔のような、じんわりとした美しさなんです。真鶴出版の出版物でも、そういった「愛おしさ」を目指しています。スパッと切りつけてくるようなデザインではなくて、じんわりと「いいな」と思えるデザイン。

愛おしさを目指した結果、手作業を取り入れているものもあります。
例えば『日常』という雑誌では、表紙の絵を書店員さんに書いてもらったり、山や海で拾ってきたものを箔押し機で1枚ずつプレスしたり、レンガを細かく砕いて膠で溶いて塗ったり。
大変ですが、そうすることで、ぬくもりも生まれるように思います。
顔の見える誰かの仕事が、暮らしにダイレクトに影響する

──真鶴出版を始める前は、東京のIT企業で会社員として働いていたと伺いました。そこから住む場所もお仕事もがらりと変化して、10年。暮らすことと働くことが、どのようなつながりを持って広がっていっていますか?
川口さん:真鶴は小さいまちなので、自分のアクションがすごく反映されやすいんです。例えば、パン屋をやりたい人がやってきたので誘ってみたらパン屋ができて。一つのパン屋ができるだけで、まちの人たちの暮らしが大きく変わります。同じような流れで焙煎所ができたり、美容室ができたりして。そうやって自分自身や町民の暮らしが、まるで「シムシティ」のようにダイレクトに様変わりして、豊かになっていくのが楽しいですね。
都市だと何かを「消費する」のが当たり前ですが、真鶴では「作っている」と感じられることも大きいです。何かを買うとしても、例えば1,000円でパンを買って、その人がまた1,000円の本を買ってくれて……と、お金が移動しているような不思議な感覚なんです。
──ものを作る大元からたどり着く先、消費される先まで顔が見えているんですね。地形から生業が生まれて、それがまちの景観にもなって。生業と暮らし、景観が密接につながっているというのは、都市で暮らしているとなかなか得られない感覚でしょうね。
川口さん:この間も、マグロがたくさん取れたという情報が町民の間で流れてきて、そうすると魚屋さんにマグロが並ぶから、じゃあ今日のご飯はマグロにしよう、みたいなことがありました。
──マグロの漁獲量が食卓にダイレクトに影響する。面白いですね。近くに住む人が持っている技術が、自分の日々の暮らしをリアルに支える。なにか困ったことがあると、単にネットで探した業者を呼ぶ、というのではなく、「●●さんに頼もう」と、人の顔がすぐ浮かぶのでしょうか。
川口さん:そうなんです。最近だと自分で色々とDIYをしているので、仲いい大工さんに電話して状況を説明すると、「こうやったら自分で直せるから、やってみて」と言われることもあります(笑)。「釘だけあとで持って行くから」って。

──良心的ですね(笑)。これから真鶴出版さんとして思い描いていることはありますか?
川口さん:真鶴の地域内と、地域外とでふたつあって。地域内では、町内でチームを作って何かを手掛けていく機会をもっと増やしていきたいと思っています。第一弾として、お土産のパッケージを制作中です。プロダクトを作ったり場所を営んだりと、今後色々と広げていきたいですね。
地域外としては、地域を超えて一緒に何かをやる機会を増やしていきたいです。例えば民間の物産展のような感じで、真鶴のみんなで別の地域に出店しに行ったり、反対に別の地域のみんなに来て出店してもらう、みたいな地域間交流をやりたいと思っています。
10年前と比べて全国的に、地域のプレイヤーが増えて、地域同士のつながりも強くなってきている気がします。地域でまとまってどこかに出店するといった動きは、真鶴だけでなく全国的にしやすくなってきたのかなと感じますね。
独立系書店やカフェ、飲食店などの地域を超えたつながりがもっと広がると、出版物の売上規模にもつながるんじゃないかと、期待を持っています。


真鶴に誰かゲストがやってくると、ご近所の「草柳商店」さんによく行かれるという川口さん。飲んだ後、楽しかった余韻に浸りながら歩いて帰る時間が、至福のひとときだそうです。