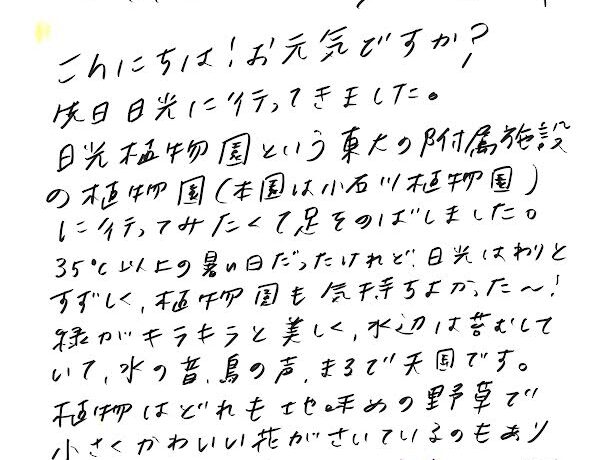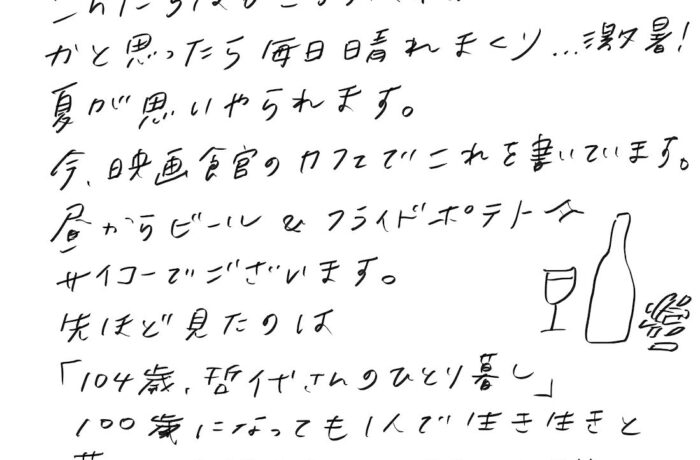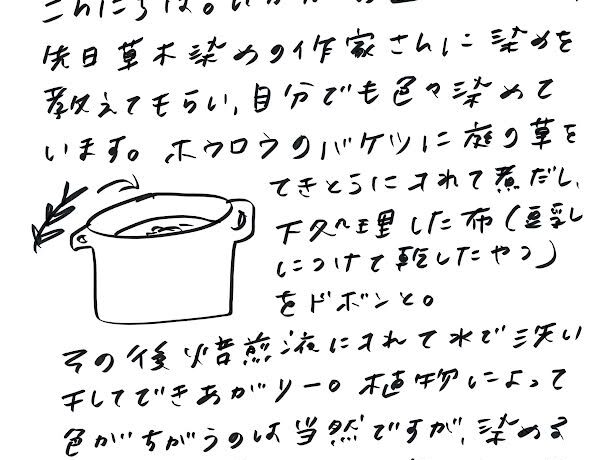第65回目のゲストは、真鶴で目にする植物の景色をモチーフに庭のようなラグを制作している『PINKNOT WEEDS(ピンクノットウィーズ)』の向井 日香(むかい・にちか)さんです。
暮らすこととつくることが地続きのように循環し、真鶴での日々の中で自然と目に入ってくる景色をラグとして表現している向井さん。
長年制作テーマとして大切に育ててこられた「植物」や、真鶴での暮らしについて、お話を伺いました。
石垣とヒメツルソバ。真鶴の愛しい景色を表現したい

東京で造花作家として活動し、草木染を施したシルクの布で手づくりした植物のアクセサリーを制作されていた向井さん。7年前にご家族で真鶴に移住されてから、真鶴で日々目にする植物の景色がモチーフになったラグの制作が始まりました。ブランド名の『PINKNOT WEEDS(ピンクノットウィーズ)』は、真鶴でよく見かけるという植物「ヒメツルソバ」の英名です。
──今日も真鶴駅から歩いてくる途中、石垣の隙間からはみだすヒメツルソバを目にしました。


向井さん:ヒメツルソバはもともと好きな植物だったんですが、真鶴では暖かいせいか群生している光景をよく見かけます。その生え方がラグみたいに可愛くて。
都内に住んでいたときは、お花屋さんの植物をモチーフにしていました。でも、真鶴に引っ越してからは、石垣のすき間に生える植物をはじめ、身近にある植物をモチーフにつくりたいという気持ちが湧いてくるようになりました。
子どもが生まれてからは、これまで扱ってきたシルクのような繊細な素材だと、毎回「触らないで」と言うのが心苦しくなってきて。子どもたちが踏んだり触ったりしてもいい素材で、植物表現をしたいなと思うようになったんです。
──「植物」はずっと、向井さんのものづくりの大切なテーマだったのでしょうか?
向井さん:わたしは、キリスト教の信仰を持つ両親のもとで育ったんですね。そのため家庭内と世の中の価値観が乖離していることに悩んでいた時期がありました。
そんな中、植物が枯れ、生えてくる自然のサイクルは、理由や原因を理解しなくても信じられる現象だと感じました。つまり、人間は完璧な理由を知らなくても、信じることができる力を持っているんです。そのような自然の力や循環を見て、植物は自分の家庭内の価値観と世の中の価値観をつなぐ象徴的な存在となり、心の支えになりました。

──現在は「タフティング」という技法でラグを制作されています。今の表現方法にはどのようにたどり着いたのでしょうか?
向井さん:最初は、シルクの布でヒメツルソバをつくったこともあったんです。でも、単体ではなく、石垣や土の部分を含めた生えている環境まで表現しないと、この植物の魅力は伝わらないなと思いました。ただ、周囲の環境までシルクの布で表現することは難しく、悩みました。
5年ほど試行錯誤した末、SNSで偶然、タフティングでつくられた作品を目にしたんです。最初はどうやってつくられているのか分からなかったのですが、いろいろと調べたところ、どうやら「タフティング」という技法らしいとたどり着きました。
今ではこの技術を使い、作品をSNSで発信される方が少しずつ増えてきましたが、私が始めた当初は全く情報がなくて。制作に使う機械も海外から取り寄せなければならず、使い方も海外のYouTubeを見て研究しました。タフティング用の糸は日本で買うと高価で、結局海外から仕入れ、国内の染色工場で染めてもらいました。手探りの連続で、最初のうちは何度も失敗しましたね。


──大変な思いをして技法を体得していったんですね。そのように高いハードルの連続だと、人によっては途中で挫折してもおかしくないと思うんですが、どんな思いが、作品として形にするまで向井さんを駆り立てたのでしょうか?
向井さん:「真鶴で出会った景色を表現したい」、ただそれだけでしたね。何年も、もんもんと悩んでいた期間があった分、タフティングに出会ってからは「これでようやく表現したかった景色をつくれる」と、迷いはなかったです。思ったとおりに作品になったときは、すごく嬉しくて、どんどん制作が進んでいきました。
──真鶴の景色と、向井さんが長年温めてこられた「植物」というテーマが、「タフティング」という技法でつながったのですね。
ラグという日常使いされるプロダクトにする上で、大切にしていることはありますか?
向井さん:子どもが踏んで楽しいようなものにしたかったので、素材はウール100%にしています。アクリルやコットンの素材の方が手入れは楽なのですが、ウールは自然な発色で、色味の定着が良く、踏み心地もいいんです。また、素材としての強さもありますね。生きている素材なので、くたっとなってしまってもスチームを当てればフワッと立ち上がります。


──お子さんたちは、できた作品を見てどんな反応でしたか?
向井さん:跳んだりはねたりしています。デパートに作品を展示したときも、当たり前みたいに靴を脱いで寝転んでいました(笑)。
暮らすこととつくることが良い循環で回り始めた

──もともと都内にお住まいだったとのことですが、真鶴に引っ越したきっかけは?
向井さん:都内に住んでいたときに結婚したんですが、夫が田舎育ちだったこともあり、東京で子どもを産んだり育てたりするイメージが湧かないから、どこか田舎に住もうという話をしていました。益子や金沢、鎌倉などいろいろなところを見て、最後にやって来たのが真鶴でした。
この地域で「泊まれる出版社」を営む真鶴出版さんが公開していた記事を読み、真鶴に行ってみたいと思っていました。偶然、知人が真鶴に引っ越して「遊びに来て」と声をかけてもらったんです。最初に訪れたのは雨の日だったんですが、夫婦ともども一発で気に入って。晴れた日に改めて来てみると、やっぱり良くて。

──山も海もすぐそばにあって、高い建物がない雰囲気も心地良いですね。
向井さん:住むことを楽しめそうな、静かな雰囲気がしっくりきました。東京でいう谷中・根津・千駄木のような下町の雰囲気があり、住む人々の暮らしが見えるまちです。
真鶴には「美の基準」という独特の景観条例があります。例えば「どの家からも海に映る月が見えるように」といった、詩的な条例なんです。その条例に惹かれて、わざわざ真鶴に見学に来る方もいらっしゃるくらいです。もともとは30年前のバブル期に、隣の熱海でリゾート開発が進んでいた時、その波を食い止めるべく、当時の町長さんが奮闘されたそうです。
──客観的な数値ではなく、受け手の想像力や余白を大切にしている、素敵な条例ですね。
向井さん:真鶴に来てから今年で7年になりますが、移住仲間もだいぶ増えました。いろんなことをしてきた人たちが集まっているので、田舎なのに東京との文化的な格差を感じないんです。それどころか、高まったぐらいです。鎌倉や葉山ではなく、わざわざ真鶴を選んできているという共通点があるので、同じような感覚を共有している仲間たちなんです。
──真鶴に移住してから、ご自身の中ではどのような変化がありましたか?
向井さん:私は埼玉出身で、海も山もない住宅地で生まれ育ちました。もともと植物は好きだったものの、いわゆる住宅地で育ってしまった自分にとって、「植物」をテーマにするにはリアリティがない。それが、コンプレックスだったんです。
真鶴に住んで数年経ってからようやく、自分の中の文化として植物の景色がちゃんと取り込まれて、植物をコンセプトとして違和感なく打ち出せるようになりました。

──植物が「どこか遠くにあるモチーフ」なのではなく、生活の身近なものとして存在し、それが自然と自分の中に取り込まれ、作品としてアウトプットされて。ご家族との暮らしがベースになって、良い循環で作品が生まれているように思います。
向井さん:矛盾がないから、嘘をついている部分がない感じがします。自然と入ってきたものを作品としてアウトプットして、それで子どもたちが遊んでくれているのが、また嬉しくて。ヒメツルソバと石が織りなす景色を表現したい気持ちはあったものの、タフティングに出会うまでは出力方法が分からず、作品をつくれないでいた期間が長かった分、今ようやく回りだした感じです。
何もできない5年間、子育てと夫婦で営んでいるピザ屋の仕事がメインでしたが、自分のベースはずっと「作家」でした。PINKNOT WEEDSとして作品をつくれるようになって、ようやくもとの自分を取り戻せたように思います。
ラグを通し、真鶴の景色を持ち帰ってもらいたい

──作品のモチーフにする風景は、どのようにしてストックしていっているんですか?
向井さん:子どもと散歩しているときや、子どもをお迎えに行っているとき、ひとりで歩いているとき。日々の生活の中で目にしたものを写真に撮ったりしてイメージを膨らませています。わざわざ見に行くよりも、仕事と子育てという日々の中で目にするもののほうが、記憶に残っています。写真をトレースするというよりも、印象として残っているものを作品にすることの方が多いですね。
──作品制作を続けてこられて、日々目にする真鶴の景色の見え方は変化しましたか?
向井さん:ただ「かわいい」と思って見ていたときよりも、ぐっと解像度が上がった気がしますね。自分の作品として落とし込むためのヒントとして、例えば植物の生え方や形といったディテールに、より目が留まるようになりました。
──幼少期のご家族の宗教観から、植物が特別な存在になったと話されていました。真鶴でのご活動を経て、今「植物」をモチーフにした制作活動を振り返ると、どのような思いですか?
向井さん:当時からずっと、植物が自分の中と外とをつないでくれる大切な存在であることは変わりません。ラグの制作を始めてからむしろ、植物の生えている環境まで表現できるようになったことで、植物の生命力に対する思いはより強くなったように思います。
高校時代からモードの世界が大好きで、文化服装学院で洋服づくりの道に進みましたが、洋服づくりは、きちんとパターンを引いて縫製しなければならず、すごく数学的。私はもともと自由にできる図工や手芸のほうが肌に合っているなと気づきました。ただ図工的・手芸的なものは、どちらかといえばアートと捉えられがち。生活の中できちんと使えるプロダクトとして昇華するのが難しいとも思っていました。
タフティングは、輪郭も自由ですし、絵を描くように感覚的に作っていけて、失敗したら戻ることができます。そういう図工的な制作プロセスでありながら、裏地を貼れば「ラグ」というちゃんとしたプロダクトにできるところが、自分にしっくりと合っています。

──向井さんの作品は、緩やかで有機的ですが、商品としてしっかりした存在感を感じます。
向井さん:プロダクトとしてしっかりしたものへのあこがれや、シルクの布のような柔らかい素材への不安感がずっとあったんですが、ラグがそうしたコンプレックスを解消してくれました。生活の中で、プロダクトとして存在してもいいよと言われている感じというか。
──これから挑戦してみたいことはありますか?
向井さん:作品をお見せできるような場所をつくり、真鶴に足を運んできた方に実際に景色を見てもらって、その後ラグをオーダーしていただくといった、小旅行を兼ねたご提案ができたらいいですね。お土産という値段ではないかもしれないですが、景色を持って帰るアイテムのひとつになれたらいいなと思います。時間をかけてでも、ぜひやってみたいことですね。
──うわー、実現したらぜひ参加したいです。「ラグにする」という視点で景色を観察すると発見が多そうですね。
向井さん:おすすめのヒメツルソバポイントが何箇所かあるんです。ディテールとして見て歩くと、より楽しいですよ。


日中はお仕事に制作活動に子育てにと、忙しく過ごしている向井さん。お子さんたちを寝かしつけた後のほっと一息つける時間が至福だそう。
静かな時間に、次のつくりたいものについてイメージをふくらませるそうです。