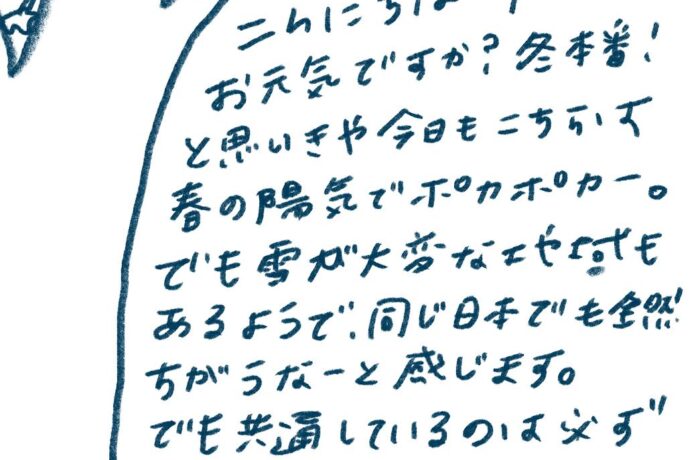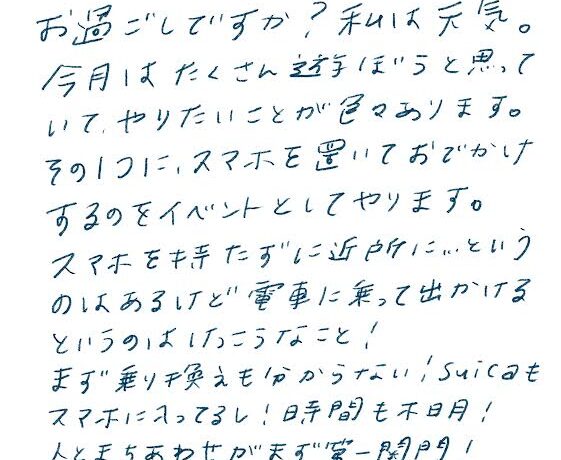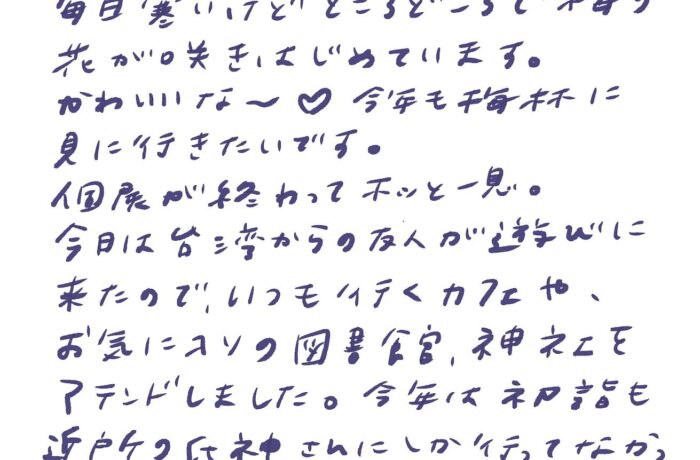今回お話を伺ったのは、東京都荒川区にある、創業約50年の銭湯「千代の湯」店長 長谷川 雄太さんです。もともと銭湯やお風呂が大好きな会社員だったという長谷川さん。あるきっかけから、4年前、千代の湯の店長へとキャリアチェンジしました。
日々ご近所さんが集い、脱衣所でおもむろに物々交換が始まる千代の湯は、まちの飾らない社交場。もともとの千代の湯の持ち味は残しながら、お客さんに心地よく過ごしていただく工夫を施したり、銭湯の裏側を見られるツアーや写真展などのイベントを開催したりと、新しい試みにも取り組んでいます。
開店前にお邪魔し、千代の湯の仕事を始めるまでのことや、まちの銭湯に対する思いについて、長谷川さんにお話を伺いました。
仕事帰りの銭湯で、ご主人にかけられた「おやすみ」という言葉

──長谷川さんは現在、銭湯「千代の湯」の店長を務めるほか、銭湯・サウナ好きユニット「ゆないと」として活動されています。もともと銭湯を好きになったきっかけは?
長谷川さん:子どもの頃からお風呂が好きでした。家族旅行で温泉旅館に泊まっても、ひとりで何回もお風呂に入りに行っていたくらいです。
社会人になった当初、実家から自転車で10分くらいの場所にスーパー銭湯があったので、予定のない週末は入り浸っていたんです。漫画を読んで、お風呂に入って寝て……というのをお昼から夕方くらいまで繰り返して。
そんな日々を送っていたら、徐々にまちの銭湯にも興味が出て、会社の帰り道に途中下車してさまざまな銭湯に立ち寄るようにもなりました。
しばらくして西日暮里でひとり暮らしを始めたんですが、仕事帰りに三河島の「帝国湯(荒川区東日暮里)」という銭湯に行った時、ご主人が「お休み」と声をかけてくれて。すごく心に響いたのを覚えています。
ご主人は、僕だけに特別に声をかけたのではなく、お客さん全員に「おやすみ」といっていました。「ああ、いいな」と思いましたね。

──家以外の場所で「おやすみ」といわれることって、なかなかないですよね。銭湯のどんなところが魅力ですか?
長谷川さん:服はもちろん、余計なものを全部投げ捨ててさらけ出せるところですね。何も考えなくていい。お湯につかった瞬間は頭の中の余計なものが出ていきますが、お湯につかってボケーっとしているうちに、次第に思考がクリアになってアイデアが浮かんでくるんです。
銭湯に通うようになると、常連さんとも顔見知りになります。お互い名前も知らないけれどなんとなく認識し合っていて、「あんちゃん、何やってんだ」と話しかけてくれる。その距離感がすごく楽なんです。後から番台のご主人に聞くと、実は地域の町内会の会長をやっている人だった、なんていうことも。お風呂の中ではそうした肩書きが全然関係ないのも、面白いですよね。
「長谷川さん、やらない?」会社員から銭湯店長への転機

──長谷川さんと千代の湯との出会いは?
長谷川さん:もともとはお客として、何度か足を運んでいました。こざっぱりとした性格の女将さんが印象的でしたね。今と変わらず地元のお客さんが多く、まさにまちの銭湯といった雰囲気でした。
千代の湯から徒歩5分くらいの場所にある「梅の湯(荒川区西尾久)」では、毎週日曜日に朝風呂をやっているので、よく入りに行っていたんです。ある時、梅の湯が地域を盛り上げるためのイベントを開催するというお知らせを見かけて、参加したことがきっかけで、梅の湯三代目の栗田 尚史(くりた・なおふみ)さんと仲良くなって。
いろいろとお話する中で、銭湯で人手が足りないという話を耳にし、なにかできることはないかなと、ボランティアで朝風呂の掃除をお手伝いするようになりました。
──ついに銭湯の裏側に足を踏み入れたんですね。
長谷川さん:しばらくして、千代の湯のご主人が体調を崩され、女将さんもご高齢なので、銭湯を続けるのが難しくなってしまって。栗田さんから声をかけられ、千代の湯の掃除も一緒に手伝うようになりました。
当時は、コロナ禍真っ只中の時期。仕事は完全にリモートワークでした。週3日ほど千代の湯の営業終了後に掃除をして、その足で梅の湯に入って寝て。日曜日は梅の湯の朝風呂の掃除、他にも三河島の「雲翠泉(荒川区東日暮里)」という銭湯の掃除も手伝っていましたね。

──いろいろな銭湯で引っ張りだこだったんですね。お掃除に関わるようになってから、銭湯に対する見え方は変わりましたか?
長谷川さん:「こんなに大変なことをやっていたんだ」と驚きました。ただ、前職がデスクワークだったので、体を動かせるのが楽しかったですね。
──千代の湯の店長になったのは、どういう経緯だったんでしょうか?
長谷川さん:ある時、ビルとの賃貸契約が切れるタイミングできりがいいから千代の湯を廃業してしまおう、という話が出ていたんです。
ただ、ここに毎日通う近所の方にとっては、なくなると困るわけです。また梅の湯の栗田さんには「荒川区から銭湯を減らしたくない」という思いがあり、僕自身もそこに共感して掃除を手伝っていました。
結果的に、栗田さんが賃貸契約を結び直し、千代の湯は「梅の湯姉妹店」という形を取ることになりました。ただ、やり手がいない。それで「長谷川さん、やらない?」と声をかけていただいたのがきっかけです。
必要とされる場所で、力を発揮する

──会社員から銭湯経営、大きなキャリアチェンジです。最終的に銭湯の道を選んだのは、何が背中を押したんでしょうか?
長谷川さん:栗田さんとの出会いは大きいですね。前職は薬の開発に携わる仕事だったんですが、ちょうど30歳になる手前。全く違う業界で働いてみたいと転職を考えていた時期でもありました。栗田さんにも「転職を考えている」ということは話していました。
そのタイミングで、千代の湯の女将さんからも直々に「お風呂屋さん、やらない?」と声をかけていただいたんです。後々聞いたんですが、一緒に掃除を手伝っていた別の方にも、「長谷川くん、千代の湯やらないかしら」と話していたそうです。
──女将さんの期待も厚かったんですね。
長谷川さん:もうひとつの後押しになったのが、前職でとてもお世話になった専門職の同僚。再雇用でご高齢の方だったんですが、僕が退職する前に別の会社に転職されたんです。転職の理由を尋ねたところ、「必要とされる場所があるから、そこで力を発揮したい」とおっしゃっていたことが、記憶に残っていました。
千代の湯はご縁があった上に、自分を必要としてもらっている。アルバイトとして関わることはできたとしても、丸ごと任せていただける機会なんてそうそうないですよね。
このまま普通にサラリーマンとして働き続けていたとしたら、数十年後、自分が死ぬ直前に「ああ、あの時に風呂屋をやっていれば」と絶対後悔するなと思ったのが、最後の一押しになりました。
──奇跡的なタイミングだったんですね。そこから4年。これまでどんな試行錯誤がありましたか?
長谷川さん:まずは、とにかく掃除を徹底的に行ってきれいにするところからスタートしました。宣伝のためのSNSのほか、それまでなかったドリンクやアイスなどの取り扱いも始めました。幸い、女将さんとご主人が丁寧に使い続けてくださったおかげで設備はきれいだったので、まずは目に見えるソフトの部分から少しずつ変えていきました。


──長谷川さんが店長になったことで、常連さんたちの反応はいかがでしたか?
長谷川さん:女将さんが常連さんたちに話してくださっていたみたいで「ああ、あんたね」と受け入れてくださいました。
当初、週3〜4日しか開いておらず、女将さんの体調によっては休む日もありました。常連さんたちはもちろん事情は理解していたものの、僕が継いだことで「毎日同じ時間に空き、営業している」という状態に戻れたので、いろいろな方から「ありがとう」といわれましたね。
──地域の方たちの暮らしのインフラを、再び維持できるようになったんですね。千代の湯では、マニアなツアー(※)とコラボした「銭湯の開店準備して一番風呂に入るツアー」や、フォトグラファー・遠藤宏さんによる小屋の写真展など、イベントも定期的に開催されていますね。
長谷川さん:銭湯は飲食店と違って中が見えないので、初めて行くときにちょっと緊張しませんか?それが原因で銭湯に行きにくい、という方の声も耳にしたことがありました。「銭湯の開店準備して一番風呂に入るツアー」は、常連さんではない人たちに向けて、銭湯の中を見て知ってもらって、ハードルを下げる目的で開催しました。
小屋の写真展は、常連さんと一見さん両方に向けて開催したイベントです。遠藤さんの写真と千代の湯の相性が良く、大成功でしたね。常連さんからの評判も良く、僕にとっては一番の褒め言葉でもある「なんかいいね」という感想をたくさんいただきました。
会期終了後に写真を剥がしたら、「寂しい」といわれたくらいです。
※マニアなツアーとは
さまざまなジャンルのマニア・専門家をガイドにお招きして、みっちり解説を受けながら様々な体験をするツアー。運営は「マニアな合同会社」。
https://note.com/manianananika/


様々な世代の人たちが気軽に情報交換できる場に

──銭湯でのお仕事を続けてこられて、長谷川さんご自身の、暮らすことや働くことへの向き合い方に変化はありましたか?
長谷川さん:引き継いだ当初は仕事とプライベートの境目がないのをストレスに感じたこともありましたが、今は楽しくなってきましたね。例えば誰かと遊んだり喋ったりした時にふと思い浮かんだアイデアを、そのまま仕事に活かせることもあります。
また地元の方に顔を知られている仕事なので、より「ここに住んでいる」という地に足がついた感覚を持てるようになりました。
「体力がしんどいから休みたい」、「どこか顔を知られていない場所へ行きたい」と思うことも正直ありますが、それを含めても仕事が楽しいですね。
──これから千代の湯をどう育てていきたいですか?
長谷川さん:この先も今と変わらず、人が気軽に集まれる場所でありつづけたいなと思います。常連さんと新しく引っ越してくる若い方たちが互いに混ざり合って情報交換をして、ニコニコしながら帰っていけるような場を、これからも作り続けていきたいです。
「尾久といえば、梅の湯と千代の湯だよね」という二大巨頭になれればいいですね。

──まちの銭湯は、これからどういう存在になっていくと思いますか?
長谷川さん:今は昔と違い、基本的に各家庭にお風呂がある時代。インフラとしての機能は残しつつも、銭湯の役割は今後変わっていくと思います。それでも高齢になった時、毎日家のお風呂を掃除して沸かすのは大変ですよね。そんなときに近くに公衆浴場があれば、週に2、3回でも通うことができます。
みんながお風呂に入って、裸でぺちゃくちゃしゃべって、「あんた最近太ったね」「痩せてるけどちゃんと食べてる?」みたいな、しょうもない会話ができる場所として、まちの銭湯が残っていくといいですね。
若い人たちには、「もうひとりのおじいちゃん・おばあちゃん」を作りに来てほしいです。千代の湯の女将さんも、僕にとってはもうひとりのおばあちゃん。いつも来てくださる常連さんは、僕が忙しくて番台にいない日があると「大丈夫?」と心配してくださいます。体調を崩して休まなければならないときも、「休んで」と声をかけてくださいます。
うちに限らず他の銭湯もそういう形になると、今後形を変えて長く続いていけるのではと思っています。


本を読むのが好きな長谷川さん。休みの日は、よく本屋さんに足を運んでいるそうです。好きなジャンルは小説やエッセイ。偶然手に取って買った本が、読んでみたら面白かったという瞬間が、至福だそうです。千代の湯の脱衣所一角には、長谷川さんの私物の本を貸し出し・販売する本棚も。